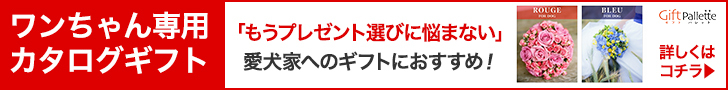文:はくたく
文:はくたく
さて。
ふてぶてしき虎猫・『とりま』の次に俺が出会ったのは、生後二ヶ月ほどの子猫であった。
『とりま』が去って数ヶ月。
事故で重傷を負った俺の体もずいぶん回復してきて、飯も普通に食えるようになっていた頃のことだ。
ある日曜の朝。俺は何の気なしに部屋のドアを開けて外を見た。
ふと、予感がしたのだ。声でもなく、音でもなく……気配としか言いようのない、何かが外に来ている感じだった。
周囲を見渡しても、誰もいない。気のせいかとドアを閉めようと下を見たら、そいつがいた。
●
子猫は俺を見上げて嬉しそうに声を上げた。
灰色の虎模様。
といえばイメージできるであろうか。ロシアンブルーほど濃い灰色ではなく、アメショーほど模様がクッキリはしていない。
そういう色彩の、掌に収まるほど小さな猫が俺の部屋の前にいたのである。
●
俺はしばらく迷った。
アパート生活にも慣れ、ゲームと漫画とドライブ三昧という、昼夜逆転に近い怠惰な生活を送っていた俺に、こんな小さな猫を飼えるのか、と。
その時点ですでに、彼を放棄する選択肢は俺のアタマにはなかった。おそらく捨てられたと見えるこのサイズの子猫が、誰の庇護もなく生き延びることは不可能だと思えたからだ。
だが、それでも決心がつかず迷っている俺を尻目に、子猫はさっさと俺の部屋に侵入してきてしまったのであった。
入って来ちゃったからにはしょうがない、飼おう。そう自分を納得させた俺は、困ったことになったと思いつつも、どこかウキウキしていたのである。
●
猫を本格的に飼育するのは、それが初めての経験であった。
トイレ、猫砂、子猫用の餌、おもちゃなど、ショップの店員に聞いて必要な物を買い集め、部屋を猫仕様に変えていく。
彼が子猫でなかったら、もしかするとまた『とりま』のようにいい加減な飼い方で終わっていたかも知れない。だが、生後二ヶ月の子猫に手を抜くことはできなかった。
とはいえ、まず獣医師に診てもらいに動物病院に行く、という頭も俺には無かった。
カネが無い、というのもあったが、一見して健康そうな生きものを持ち込むと、嫌な顔をされそうに思ったからだ。もちろん今は、むしろちゃんと獣医師に診せることから飼育は始まると分かっているが。
●
子猫の名は『ぽんぽこりん』ということになった。
あまりにお腹がポッコリ出ていたからだ。それは、まるでリンゴを丸ごと呑み込んだような感じで、腹ぺこの時もポッコリ具合は変わらない。
それでも、非常に元気ではあったし、友人の飼っていた『メル』のお腹が出ているのを心配して獣医師に診てもらった時には、単なる肥満だったこともあって、余り心配はしていなかった。
ところがある時、俺は『ぽんぽこりん』の肛門周りに小さな白いうねうねした生物を発見した。その生物は、一見してサイズも色も形もメロンの種のように見えた。だが、動いている。
初めて見るその生物は、目も口も触覚も見当たらず、足も羽も無い。だから歩いたり這ったりは出来ないようであった。
この子猫のお腹は、やはり普通ではなかった。寄生虫持ちだったのである。
●
どうりで、トイレの後にいつも肛門周りを気にしていると思った。はじめてネコの排便を管理したので、何が普通か分からなかったのだ。
くっついていた寄生虫の名称は「瓜実条虫」。いわゆるサナダムシの仲間であった。
もともとは、全長五十センチにも達する長い一匹の寄生虫なのだが、体の後半は一節ごとに簡単に切れるようになっており、その一節一節は体外に排出される。もちろん体外ではすぐに乾いて死んでしまうが、その内部に卵を持っていて、中間宿主であるノミの幼虫に食べられるのを待つのだ。
これに寄生されたノミは動きが鈍くなり、猫の口に入りやすくなるということのようだ。
●
それにしても、まだ子猫なのにお腹がポッコリふくれるほどでかい寄生虫がいるのは不思議であった。
瓜実条虫は命に関わるようなことは滅多にないらしいが、一個体がでかいのである。
俺は『ぽんぽこりん』をすぐに獣医に連れて行き、駆虫薬を処方してもらった。それから数日して、粘膜状のものに包まれた奇妙な便が排泄され、彼の名の由来であったお腹はスッキリとなったのであった。
そう珍しい寄生虫ではないから、コレを見たことのある飼い主の方も多いと思うが、やはり初めて見るとびっくりするものだ。
●
しかし、寄生虫というものは、野生生物にはほぼデフォルトであって、それがまったくいない個体など滅多にいない。
大学在学時、『動物形態学実習』という授業で、様々な生物を捕獲したりもらい受けてきたりして解剖したが、魚、カエル、ヤモリ、ヘビ、鳥類から哺乳類に至るまで、野生の生物でなんらかの寄生虫を飼っていないものはほとんどいなかった。
だが、野生生物にとって寄生生物は、致命的なものであることは少ないらしい。
それどころか、消化を助けていたり、免疫力を向上させていたりして、いた方が良い場合すらあるようだ。
●
ところが、飼育下の場合は少し様子が違う。
狭かったり、高密度で飼われていて他個体の排泄物が口に入るような飼育環境下だと、互いに何度も繰り返し伝染し合ったり、複数種の寄生虫が一度に寄生したり、本来寄生しないようなものまで寄生したりして、健康に大きな害を与える場合がある。
駆虫薬には即効性はあるが、基本的に持続性は無いから、せっかく駆虫しても飼育環境が改善されない限り、何度でも再感染する場合があるということでもある。
猫を拾った場合に、最初に獣医師に連れて行くことはもちろんだが、ノミの幼虫の住処や餌となるものを無くすなど、飼育環境を清潔にすることも平行してやった方がいいのだ。
●
ノミの幼虫は、猫のフケ、人間の食べこぼし、ネズミの糞、成虫のノミの糞など、様々なものを食べて成長する。部屋に掃除機を掛けるのはもちろん、猫の寝床やトイレのリフレッシュ、屋根裏や床下の掃除などもやった方がいいわけだ。
『ぽんぽこりん』には、目立つほどノミはいなかったが、獣医師の勧めでノミとり首輪を装着した。そして、獣医師のアドバイスに従って部屋を掃除した。
ズボラな学生だった俺である。部屋の清潔さは、結局保たれはしなかったが、幸いなことに、彼は寄生虫に再寄生されることもなく、すくすく育って数ヶ月で若猫となったのであった。

さて、まだ猫を飼うということがよく分かっていなかった当時の俺は、『ぽんぽこりん』を自分の外出時に外に出すようになった。
ずっと室内に閉じ込めておくのは、猫らしくない、と思ったからだ。
責任を持って飼うつもりはあったが、猫はその辺をうろつくものという先入観があった。
オス猫だったから、あの『とりま』のように逞しく育って欲しくもあった。だが、それは大きな勘違いであったのだ。
●
大人になったオス猫は、愛を求めてひとりで旅立つもの。
愛、すなわち自分好みのメス猫と、落ち着ける場所である。また、別のオス猫に追い出されたり、犬やカラスに襲われたりもする。外は危険で一杯なのだ。
『ぽんぽこりん』が俺の前から姿を消すのに、それから一週間とかからなかった。俺は近所を探して回ったが、もう二度と彼と会うことは無かったのである。
そうなることは猫として自然、といえばそれまでなのだが、俺は深い考えもなく外に出したことを、激しく後悔した。
猫の習性や自然の敵だけの話では無いのだ。交通事故に遭ったかも知れない。自分でとれる餌は少なく、以前はなかったFIVなどの病気もある。俺の不勉強と無思慮で死なせてしまったとすれば、本当に申し訳ないと思った。
●
現在も俺は、放し飼いというのは、猫にとって不適当な飼育法だと考えている。
何故、猫の放し飼いは不適当だなどと言うのか。反発を覚える方もおられるだろう。
前提として、あくまで『現代日本のほとんどの地域では』と条件を付けておく。過去の日本では、あるいは現代でも他国、他地域では、更に言えば日本国内でも、限定された状況では、放し飼いや野良猫の存在が容認されうる状況もある、と思うからだ。
●
たしかに俺が子供の頃は、猫は外飼いが当たり前で、野良猫がいるのも街にとって当たり前の風景であった。
某ご長寿アニメの主題歌に代表されるように、野良猫というものは、社会の一部として認識されてきたのだ。それが、良い悪いは別として、だが。
しかし、俺の思う『一般的な現代日本』では、やはり猫の放し飼いは不適当だと言わざるを得ない。それどころか、猫に限らず人の住む場所に他の生物が暮らす余地は、ほぼ認められていないのが現状だと思う。
●
そんなことはない。
と、仰る方もおられるかも知れない。
「花壇にチョウが来た方が嬉しい」
「ベランダに小鳥が来るよう、餌台を作っている」
「軒下のツバメをそっと見守っている」
「水質が改善されて近所の川には魚が戻ってきた」
そういう話は、都会でも山ほどある。だが、そういう人はチョウの幼虫がどんな姿をしていて、何を食っているのか、知っているだろうか。
●
知っているなら、何故、毛虫や芋虫を殺虫剤で駆除するのか。
小鳥が普段、何を食べているか知っているのだろうか。
知っているなら、何故、公園や街路樹周りの草を徹底的に無くし、その餌となる小さな虫が住めないようにするのか。
川の魚も同じである。水質が良くなれば、それは多少数は殖えるだろうが、ガッチリ護岸し、岸際の草を取り除けば、住める種類は限られてしまう。
小鳥はよくて、カラスはダメなのか。
チョウは愛でて、ハチとみれば殺すのは何故か。
●
生きものはすべてつながっていて、それぞれがそれぞれを利用し合い、助け合って、生態系を作っているのだから、何かを排除するということは、すべてを排除することにつながると、どうして分からないのだろうか。
正直言って、カラスがその辺に巣をかけようが、街路樹に毛虫がいようが、アシナガバチが軒下に巣を作ろうが、放っておけばいいと俺は思っている。
●
そりゃあ、営巣中のカラスもハチも、近くに行けば襲ってくるし、毛虫に触れば刺しもするだろうが、要は近寄らなければ良いだけの話。近寄らずに済ませられないような場所なら、駆除もやむを得ないだろうが、そうでもない場合でも、見つけたら即駆除という現代日本の風潮は、やはりおかしい。
俺はビオトープ管理士なので、依頼があれば街中に池を作ったり、せせらぎを作ったりもする。だが、そこにカエルが集まってくると「うるさい」と苦情が出る。「カエルが集まるとヘビも来るだろうからダメ」と言い出す人もいて、そんならビオトープなんか作らず、舗装して駐車場にでもしておけと言いたくなる。
●
排斥されているのは、べつに野良猫だけではないのだ。
ハッキリ言って、野良猫は野良猫として放っておくなら、それでおしまいの話だろう。
目くじら立てて追い回したりはしない代わりに、過剰に餌をやったり、部屋に入れてやったりもしない。
たまには小鳥や金魚を襲われ、おかずの魚を奪われ、庭にうんこもしていくが、毎日気になるほどではない。
そういう落としどころが許される社会であれば、TNRも地域猫も必要なくなるのかも知れない。
●
だが、今はそううまくはいかない。
猫保護派の人は『人間のせいで可哀想な目に遭っている猫と共存するくらいのことで、何をごちゃごちゃと』という論理を持っているし、猫反対派の人は『何が猫だ。人間の生活環境が最優先だろう』という。
こんなどこまで行っても平行線のところへ持ってきて、猫の数……いや正確には地域の猫密度が増えれば、そりゃあ問題にもなるだろう。
●
とはいえ、俺はここでこの問題に波紋を投げかけるつもりはない。
ここまで言っておいてなんだが……いや、ここまで言ったからこそ分かるかも知れないが、誰かが何か主張したから変わるってもんでもないし、猫だけ守ればいいってもんでもないからだ。
ただ、俺自身の体験をご紹介することで、それを読んだ誰かに少しだけでも、猫、そして生きものとのつきあい方について考えて貰えばそれでいいと思っているのだ。
文:はくたく
――前話――
――本シリーズの最初の記事です――
●
この記事は、下記のまとめ読みでも読むことが出来ます。
この記事は、下記の週刊Withdog&Withcatに掲載されています。
●
――おすすめ記事です――